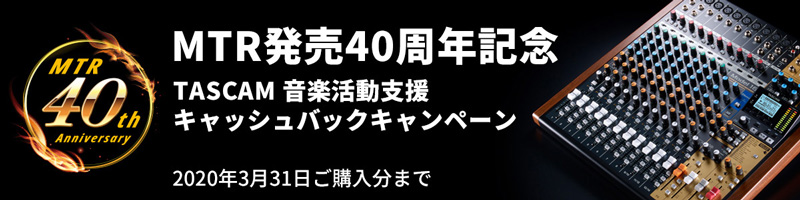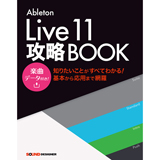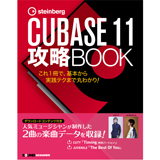TASCAM MTR発売40周年記念企画
80年代、宅録ブームをけん引したカセットMTRの名機「TEAC 244」とは?プロデューサー根岸孝旨が明かすアナログ多重録音の秘技! & 最新デジタルMTR「Model 16」の魅力に迫る!
80年代、宅録ブームをけん引したカセットMTRの名機「TEAC 244」とは?プロデューサー根岸孝旨が明かすアナログ多重録音の秘技! & 最新デジタルMTR「Model 16」の魅力に迫る!
2019/12/26
1979年にティアックから世界で初めて4トラックMTRとミキサーを一体化した「カセットMTR」が発売された。それから長い月日が過ぎ、記念すべき40周年を迎えた2019年に、進化したMTRの最新モデル「Model 16」が登場した。ここでは、カセットMTR時代から同社製品を愛用してきたプロデューサーでありベーシストの根岸孝旨氏に、MTRの思い出を、そして記事の後半ではティアックの松野陽介氏に最新モデルの魅力を語ってもらいました。
──根岸さんが、初めてMTRに触れたのはいつ頃だったのですか?
根岸:確か大学を出てプロになってからですね。米米CLUBに林部直樹くんというギタリストがいるんですけど、当時、彼の家に遊びに行ったのがきっかけでした。その時、彼はカセットMTRで多重録音をやっていて、それを見て面白そうだなと思ったんです。
──林部さんの家に行って、初めて多重録音の概念を知ったということですね?
根岸:はい。これは便利だなって。その時に「ピンポン」という言葉を初めて聞いたんですよ。「これ4つまでしか入らないじゃん。だから、3つ入ったらそれをまとめて1つに移動させてさ」って教えてくれて、「へぇ~、そんなことがこの中でできるのか。それスゲェ」と思って。それからしばらくして、PORTASTUDIO 244(以下:244)を買いました。今だったら、1日あれば使い方をマスターできると思うんですけど、当時はどうやって使うのかがまったくわからなくて、まず「ゲインって何?」っていうところから始めましたね。マニュアルも見ずに触りながら、わからなくなると持っている人のところへ行って教えてもらいました。
──リズム隊も244で録ったのですか?
根岸:そうです。当時はステレオで録るなんて考えはまったくなくて、モノラルで録っていました。ヤマハとかいろんなメーカーからデジタルドラムが出始めた時に、ちょうどパール兄妹の窪田晴男くん(g)が、リズムマシンを買い替える際に僕にローランドのリズムマシンTR-808を3万円で譲ってくれたんです。今は中古市場で50万円くらいで取り引きされていますけど。それを屋敷豪太くん(ds)に一度貸し出したりもしました。
──リズムトラックはTR-808をモノラルで244に入れて、ベースをもう1トラックに入れてといった具合ですか?
根岸:はい。今でもそうなんですけど、宅録の時はドラムとギターを先に入れて、本職のベースを最後に入れるんです。本チャンのレコーディングの時は、グルーヴ重視でドラムとベースを先に録りますけど、自分で作曲する時は、色々やってみてから、最後に「ベースどうしよう?」って考えます(笑)。
──マルチを使うようになって曲作りは変わりましたか?
根岸:最初、僕はベーシストとしてあまり売れていなかったので、20代の半ばは作曲の仕事の方が多かったんですよ。で、当事は、作曲家とアレンジャーというのは別物で、僕、作曲の依頼が来た時に喜び勇んでドラムとかギターとか入れて提出したら怒られたんです。「お前にアレンジは発注してない。余計なことするな、わかんなくなるから、純粋に曲を書いてこい」って言われて。で、僕はMTRで作ったデモを持っていくじゃないですか、そうすると、「バカヤローこんなんじゃわからない。すぐ会議室を押さえてやるから、そこで、ギター弾いて録音し直せ」って。せっかくこれでオケ作って行ったのに怒られちゃうんです。でも自分は楽しいので、他のアレンジャーさんはどうするのかは置いておいて、自分だったらこうやるのになってのをそこで作ったりしてました。
──そういう時代だったんですね。80年代前半から半ばですね。
根岸:今は逆ですけどね。
──曲作りには役立ったんですね。
根岸:そうですね。本当に僕がアレンジャーやプロデューサーができるようになったのはMTRのおかげです。僕は当時から譜面が苦手だったので、自分でやってみないとわからないわけです。特に家が当事木造アパートだったので、ピアノとか弾けなくて全部ギターで作っていて。でも、そのおかげでギターアレンジができるようになりました。ギターメインのアレンジで、何でもかんでも考えるってやっていたので。特に、90年代のグリッドポップ、グランジロックのブームのおかげで、急に仕事が来るようになったんです。今もそうなんですけど、DTMの時代になりコンピューターの音源をいっぱい使うので、キーボードプレイヤーの方がアレンジの仕事が多いと思うのですが、90年代の特に後半はグランジロックブームのおかげで、キーボードの人達のちゃんと勉強しすぎちゃったアレンジよりも、グランジロックの無茶苦茶なコードとか、何だこりゃみたいな雰囲気のアレンジができたことで、僕とかに仕事がたくさん回ってきたのだと思います。
──根岸さんは何年くらい、244を使われたのですか?
根岸:実は、90年代の初めにサザンオールスターズのサポートをやることになって、その頃はベーシストとして忙しかったので、手放してしまったんですね。90年代はイギリスのオアシスとか、アメリカのニルヴァーナやパール・ジャムのおかげで、ロックがすごく盛り上がっていましたけど、あの時代が僕にとっての黄金時代でした。でも、頭の中で彼らの音を想像しているだけじゃ作り方がわからないじゃないですか。なので、244でギターを重ねたり、組み合わせたりしたら、彼らみたいな音が作れるかもしれないって試したりしていましたね。それ以前は実験することもできなかったので、244様様でした。
──その後に、488を買われたとか?
根岸:僕が今もやっているDr.StrangeLove っていうバンドが、90年代にアメリカでレコーディングをすることになって、僕のリクエストでチャド・ブレイクをエンジニアに起用してもらったんです。当時、チャド・ブレイクがシェリル・クロウの作品を手掛けて爆発的な大ヒットを出したばかりの頃で、彼はラテン・プレイボーイズというバンドもやっていました。で、その音がすごくカッコいいんです。何でだろうと思っていたら、実はタスカムの244で録っていると。それを聞いて驚きましたね。その話はアメリカで聞いたんですけど、ちょうどその時、ラテン・プレイボーイズが2ndアルバムを録っていたんです。「2ndは音がいいぞ」って言われて、「何で?」って聞くと、今度は8トラックのTASCAM 488で録ったと。それを聞いて、「それは買わなきゃいかん!」と、日本に帰ってきて慌てて買ったというわけです。
──ラテン・プレイボーイズは、録りで488を使っていたのですか?
根岸:そうです。要するに自宅録音なんです。ラテン・プレイボーイズって、ロス・ロボスの2人とチャド・ブレイクと、ミッチェル・フルームの4人なんですね。ロス・ロボスの2人が488で宅録したものを、チャド・ブレイクがスタジオでマルチに流し直して、そこでまとめる。だから、基本の音は488で録っていたんです。ピンポンとかしながら録ったものを、スタジオで24トラックのアナログ・テープレコーダーに落としていたんですよ。当時のフルアナログ・レコーディングです。
──90年代でですか?
根岸:そうです。チャド・ブレイクは完全にアナログにこだわっていて、テープに録音していました。僕らの時も、リズムとかオケを日本で録ったものがあったので、アメリカにそれを送る時に、「さすがにアメリカはデジタルの48トラックだろう」と思って、アナログテープの24チャンネルで録ったものをデジタルの48チャンネルにわざわざコピーし直して持って行ったんですよ。そしたら「バカ野郎、何でアナログで持ってこないんだ!」って、チャド・ブレイクに言われました(笑)。「音も時間も無駄じゃないか」と。
──チャド・ブレイクは、普段から24チャンネルのアナログ・テープレコーダーを使っていたんですか?
根岸:普段は24チャンネルでしたね。コンソールはAPIで、コントロール部分だけがニーヴのフライングフェーダーでした。EQとかも「どうしたい?」って聞かれた時に、「もうちょっとハイがあった方がいいかな」って言うとガッて思いきり上げて、「いや、もうちょっと少なく」って言うと、「間はないからどっちかを選べ」って言うんです。今はPro Toolsなので、全部録音した後で考えればいいですけど、当時は1つ1つをその場で決めなければならなかった。だから、ずっと集中しているんですね。後で直せばいいという考え方ではなくて。レコーディングの決断力が身に付いたのも実は488のお陰なんですね。ちなみに、今僕がやっているCoccoも全部無しです。歌もピッチ直しとかしないですし、テイク選びだけです。基本はアナログ精神で行こうと。その方が緊張感がすごくありますね。あと、アコースティックな音楽を切り貼りしちゃうと、僕が間違えそうになっているところもスルーできるので、僕のアコギはつながしてもくれない。最後は通して弾けって。
──488はアメリカで見て買われたとお聞きしましたが。
根岸:はい、買ったんですが、なんか調子が悪くてですね。当時、スガシカオ君が借りていた場所を使ってもいいよって言われていて、そこに置いておいたんですけど、いつの間にか使わなくなっちゃって。それも誰かに譲ちゃったかな? 8トラの方は、数えるほどしか使ってないと思います。
──このころから同期ができるようになってきましたよね?
根岸:ただ同期というのはまったく興味がなくて。本当に今まで、できるだけ避けて通って来たんです。実は若いころにYMOのローディをやってたこともあるので、そっち関係の知り合いも多いんですよ。彼らを見てると、凄すぎて、今からやっても追いつけないし、僕が中途半端に始めるよりも、専門家に任せればいいと思ってました。凄い時代でしたからね。「これ自動で演奏しちゃうの」これみたいな(笑)。
──カセットテープにこだわっていたことはなかったですか?
根岸:貧乏だったので全然こだわってなかったですね。クロームテープなんかは高くて買えなかった。
──でも、クロストークとかノイズとかその辺も段々気になってきますよね。
根岸:気になってきますが、気にしない(笑)。カセットテープのこの幅でクロストークは当たり前だろっていう。これをこのまま製品にするという感覚はまるで無かったので自分が分かれば良いやって感じでしたね。
──本当にデモテープ的な感じですね。
根岸:ただピンポンするときは凄く考えましたね。何度もやり直ししました。
──ピンポンする順番はありましたか。歌は最後にするとか。
根岸:歌はやっぱり最後でした。ピンポンで一番役に立ったのはコーラスですね。とにかく声がダビング出来るっていうのが画期的でしたね。コーラスを試せるっていう。
──何トラックぐらい使われていたんですか。
根岸:8パートぐらいやってましたね。
──8パートもですか。
根岸:最後の方はサーサー言ってて何が何だかわからなかったですけどね(笑)。
──ピッチコントロール(倍速)は使用していましたか。
根岸:もちろん使ってました。ケロってました。昔はチューナーじゃなくて音叉でやってましたから時々音叉鳴らすの忘れて録音した時とかこれで調整してました。あと、女の子に曲を提供する場合にわざとそれをやってました。声がちょっと高めに聴こえて女の子っぽくなるので気持ち悪がられましたけど(笑)。でも、今思うとこのピッチコントロールが一番楽しかったかも知れないですね。ピッチを変えて自分じゃない人が歌ってるみたいな。後々クィーンがこの手法だったんだと知るわけですよ。あれ人間の声じゃねえだろと思ってたらテープの回転落としてたんだっていうことが244を買って使ってみてわかりました。色んなことを覚えましたねこれで。
──録音レベルに関しては?
根岸:もちろんギリギリまで上げて録ってました。僕はテープコンプ好きなんで。歪はまずテープで歪ませるっていう(笑)。歪ませちゃいます。昔から。
──ドラムもベースもギターもですか。
根岸:はい。テープで歪ませます。プロの現場で普通のポップスのときはそんなことしないですけど、当時YMOのエンジニアだった寺田さんとかは「SSLの卓の歪が一番かっこいいんだよ!」とかいって「スタジオのアシスタントには内緒な」ってメーター真っ赤になるまで上げていました。「おぉ~かっけぇ」みたいな(笑)。僕の周りのエンジニアはみんな真っ赤でした。まぁ、もちろん音楽によるんですけどね。カーペンターズみたいな音楽で歪ましちゃいけないですけど(笑)。
ティアック:僕が初めて根岸さんとお会いした時に「僕もTEAC使ってたよ」ってお話いただいて「アナログで録る音とデジタルで録る音はグルーブが全然違うんだよ」とおっしゃっていたのがずっと印象に残ってるんですよね。
根岸:そうなんですよね。最近は使わせてはくれないですけどアナログのテレコがあるスタジオに行くと「ねぇ~使っていい」って未だに聞くんですよ。「何でですか?」って聞かれるんですけどテープコンプが欲しいんですよ。
──なるほど。
根岸:僕はまだ48(PCM-3348)が出る前からスタジオで仕事していたんで、最初48の音を聴いた時は「なんでこんなにドラムとベースが仲良くしないんだろう」って思ってたんですね。やっぱりアナログで突っ込むと細かいズレって気にならないんですね。全然、音楽として一体化するんですよ。特に現代のPro Toolsとかが中心になるとそういう縦の線(時間軸)が気になっちゃうんですよね。
──よく言われますよね。
根岸:昔は気になんないんですよ本当に。逆にビートの幅があった方がかっこいいんじゃないかっていうね。Logicなんかで録っちゃうとただのヘタクソだなって思ったりして。まぁでもこういう流れになってきたのもきっかけはビートルズですからね。
ティアック:そうなんですよね。
根岸:ポール・マッカートニーとかが「もっとダビングしたい」「一人でこれ全部やりたい」って言い出したんでこういうことになってるんで。「せーの」で録音する時代だったら関係ないんですよね。そんなものいらなかったんだから。だから僕は人間一人の力よりも人がいっぱい集まった方が音楽としては良いんじゃないかと思うんですけどね。まぁプライベートなその人の魅力的なものを知りたい場合はプライベート色が強いのも良いとは思うんですけど。
ティアック:難しい問題ですね。
根岸:そんなことを言ってると時代から取り残されるんで気を付けないと(笑)。
 ▲最新デジタルMTR「Model 16」を試奏する根岸さん
▲最新デジタルMTR「Model 16」を試奏する根岸さん
──丁度、時代の流れという話になったところで、今日はティアックさんの最新デジタルMTR「Model 16」をお持ちいただいたので一緒に触ってみませんか。
根岸:これルックス的にはMTRには見えないですけど。
──ミキサーですよね。
ティアック:最新のデジタルMTRはこういう形なんです。
──デジタルミキサーではないんですか。
ティアック:ミキサーはアナログなんです。でこれが全部マルチで録れるんですよ。
根岸:レコーダーなんですか? 音は何で録るんですか?
ティアック:SDカードです。ライブのレコーディングミキサーです。ミキサーで使えてそのままマルチ録れるというのがポイントです。それぞれのRECボタン押しておくと、使ってるトラックがすべて録音されます。
根岸:あっ!ライブレコーディングがすぐできるんだ。
ティアック:あとこのMTRっていうスイッチを切り替えると、そのトラックはオケを流しながら他のトラックで録音もできます。またオーディオインターフェースにもなりますので、PCをつないでおいてこのチャンネルはオケに使う、このチャンネルはDAWにも録音するとかができますね。
根岸:このスイッチは
ティアック:それはコンプですね。
根岸:これはアナログっていうのが良いですね。じゃあここで歪ませたりできるっていう(笑)。
ティアック:もちろんできます。あと弊社で最近力を入れているのがマイクプリアンプの所で、TASCAMでマイクプリってあまりイメージないかもしれませんが、NHKさんやTBSさんなどの放送局のポン出し機とか音声レコーダーってほとんど弊社製品なんですよ。そこで放送局から求められるのがとにかく色付けはしないで欲しい。それとノイズが少ないことなんですね。そういう技術が蓄積されてきたので他にもフィードバックしていこうということでこの「Model 16」にも使われているんです。あとビンテージマイクを使う場合も有効ですね。
──結構ばらつきがありますよね。
ティアック:「Model 16」は放送局で使われるようなプリアンプの回路を使っているのでそういう手ごわいマイクが来ても対応できる仕様になっているんです。
根岸:これでお幾らなんですか。
ティアック:メーカー希望小売価格で115,000円になります。
根岸:安っ!244は198,000円でしたよ。4トラックで。これなら一台持ってても良いな。これがあったら自分のライブとかの録音もできそうですよね。
ティアック:カフェライブとかだったら丁度良いかも知れないですね。
根岸:ライブハウスみたいに専任の人が付けられないような会場だったら便利だね。MTRってここまで進んでるですね。今度使い方教えてください!
メーカー担当者にMTR40周年最新モデル「Model 16」の魅力を直撃!

ティアック株式会社 音響機器事業部 営業統括部
統括部長 松野陽介氏インタビュー
──MTR40周年おめでとうございます。MTRの初期からハードをリリースされていた印象が非常に強いのですが、開発することになったきっかけみたいなものはあったのですか。
松野:ありがとうございます。弊社の歴史においても非常に大きなエポックメイキングを実現した商品の一つであり、世界初の4トラックカセットテープMTRとして144をリリースしました。それが、1979年の事で、今年で40周年となります。開発のきっかけとしては、当時、本当に限られたプロが業務用スタジオでしか使用する機会のないマルチトラック録音を、手軽に自宅で実現できたら楽しいだろうというアイデアが発端になったと聞いていますが、実際に、カセットテープを採用するという革新的な開発アイデアにより、サイズと価格において家庭向け商品として実現する事ができ、市場からもすぐに支持を得て一気に普及していきました。ちなみに、そのイノベーティブな精神を忘れるなという事で、本社オフィスにもいまだに一台展示しております。一般開放しておりますので、読者の皆様もぜひ一度お越しください。(ティアック本社 東京都多摩市落合1-47 1Fゲストロビーに展示)
──当初、世界的にはどの国が一番売れていたのですか。(当初から海外展開されたのですか)
松野:やはり、音楽先進国のアメリカを中心に爆発的に売れましたね。すでに海外展開は進んでおり、当時から現在までアメリカに現地法人を構えています。
──カセットMTRをリリースしてコンシューマー市場に一気に「多重録音」というジャンルが定着したと思いますが、最初からカセットMTRはイケるという確信はあったのでしょうか。
松野:それは、当然サイズの縮小と価格、家庭向けに実現できれば必ず当たるという事は確信があったと聞いています。
──カセットMTRによる多重録音が音楽業界に与えた影響は大きいと思いますが有名な逸話などありますか。
松野:最も有名な逸話としては、ブルーススプリングスティーンがアルバム「ネブラスカ」においてカセットMTRのデモ音源をそのまま本番に採用した件ですね。もちろん、カセットMTRの音質はプロスタジオのクオリティーにはかないませんが逆にカセットテープ独特の味がいいという事で採用になったようです。また、最近ではレディーガガが子供の頃に最もうれしかったプレゼントとして弊社のPORTA ONEの名前を挙げてくれており、著名なミュージシャンをはじめ多くのミュージシャンの方々のアイデアを具体化するのに役立っていたことを考えると、音楽シーンの発展に大きく貢献したといっても過言ではないと思います。最近では奥田民生さんとのコラボモデルをやらせていただくなど、改めてMTRの楽しさというものが見直されていますし、動画サイトなんかでも有名アルバムの単独トラックの音源などが公開されているなど、マルチトラックの楽しさが再認識されていると思います。
──当時は製品によってTASCAMブランドだったりTEACブランドだったりした記憶がありますが、そのあたりのブランド名義の流れを教えてください。
松野:TASCAMは、1971年にTEACのプロフェッショナル音響機器の販売会社TEAC AUDIO SYSTEM COMPANY OF AMERICAとしてスタートしました。当初はブランド名ではなく、販促のチームでした。その後カセットMTR 244から「TASCAMシリーズ」という名称で販売され、のちにレコーディングや業務用機器などプロオーディオの分野で「TASCAM」というブランド名が確立していき今に至ります。
──アナログからデジタルへとメディアが移行した時は色々と制約が無くなったと思いますが、MTRにとって一番大きなメリットは何だったのでしょうか。
松野:ピンポン録音しても音が劣化しない!(笑)といってももはや通じる世代も限られてしまいますが(笑)。実際には、デジタル化の最も大きなアドバンテージはトラック数ですね。カセットでは8トラックが限界でしたが、デジタルで個々の制約が取れましたので、開発する側としても多くの可能性を感じながら製品化できましたね。TASCAMのDP-32SDでは32トラック録音を実現しました。
 ▲TASCAM DP-32SD
▲TASCAM DP-32SD
業務用機器では1台で64トラック実現しているデジタルMTRもあります。また、バーチャルトラックでテイクを残したり差し替えたり、アンドゥーしてやり直したり、カセットテープが足りなくなって近所の電気屋に出向くという面倒くささもなくなるなど、デジタル化のメリットは多々ありました。あと、カセットMTRはMIDIシンク信号を1トラックつぶして入れなければならなかったりとかしましたからね(笑)。私も個人的にカセットMTRは使い倒したほうですが、ピンポン録音の技術は非常に高いレベルまで習得しました。もう必要ないですが(笑)。
──MTR40周年の歴史の中で一番大きい変化があったとすれば何ですか。
松野:やはりカセットテープの幕引きですね。デジタルメディアになった恩恵は計り知れないですが、カセットテープで録音するあの音はもう再現できる機器が販売されていませんので・・・。コンシューマーオーディオの世界でもアナログレコードが元気ですが、やはり人間の耳はハイレゾのデジタル音源をもってしても感じられない何かがあるんだと思うんですね。肌で聴くというか・・・そこが感動を生むというか。そういう意味では、カセットMTRで作った音の味は忘れがたいですね。
──40年の間に何度かピンチがあったかと思いますが今だから話せるものはありますか。
松野:そうですね。やはり音楽制作がDAW中心に変わってきたところでMTRが難しい局面を迎えたこともありました。しかしながら今は逆にDAWが当たり前すぎて、MTR単体機が注目を浴びるという中々面白い立ち位置にいると思います。この度発表したModel 16はデジタル環境のみでは表現できない音質や操作感・フィーリングを持ち合わせていますので、DAWレスで使うも良し、ウィズDAWも良しで、実際にDAWで完結しているクリエーターよりも、単体機との併用によりとくに音質の差別化が可能となる、クリエイターの新しい武器として注目を浴びています。あと、ちょっと作業したいときに、いちいちパソコンを起動しなくていいというのもポイントですね。
──では、その新製品の主なポイントを教えてください。
松野:アナログミキサー、MTR、オーディオインターフェースといったTASCAMの歴史でも中核をなすそれぞれの技術が集結し一台にまとまった究極のバーサタイルミキサーです。もう、DTMと呼ばれてから久しいですが、コンピューターを中心とした音楽制作環境から始められる方も多い中で、逆にこう言った直感的な操作を可能とする単体機は更なる音楽制作環境の広がりを提供します。
──どのような用途が考えられますか。
松野:そうですね、クリエイター目線ですと、自宅でアイデアを制作して、それをModel 16と共に外に持ち出してバンドレコーディングをしたり、またそれを自宅に持ち帰って自宅でミックスしたり。もちろん、DAWで編集したければ、Model 16で録音した音源をDAWで微調整したり、また、Model 16はDAWから音を戻す事ができますので、サミングミキサー的に使ってModel 16の太い音でミックスダウンしたりなど、まだまだあります。ライブでリハをして、そのリハを録音しておけば、バンドメンバーがいなくてもサウンドチェックを続けられます。また、演奏したアーティスト本人にもその音を聞いてチェックしてもらう事ができます。あと、同期オケが必要な現場でも重宝します。などなど、恐らく、Model 16でできることを全部挙げると紙面をすべて使ってしまうと思いますので、この辺にしておきますが、さまざまな場面でこのマルチトラックミキサーが威力を発揮します。
──TASCAMの目指すMTRは今後どのような進化をしていくのでしょうか。
松野:TASCAMでは読者の皆様によく知られている音楽制作用MTRをはじめ放送局から劇場、アミューズメントパークなど様々なプロ音響現場で使用されており、日々マルチトラック録音の技術を磨いております。普段何気なく耳にしている音が実はTASCAMの機器から再生されているという事も多々あるかと思います。今後、映像・照明・ネットワークなどの進化により更に複雑で高い技術を要求されるようになりますので、10年20年先においても、社会の音の一つとして今後もTASCAMのMTRから録音・再生する音をお届けし続けたいとともに、クリエーターの皆様においては更にその創作活動のサポートになることが可能な機器を開発していきたいと思っています。また、MTRに限らず、144が開発された時のようなエポックメイキングな製品をリリースして、ユーザーの皆様に喜んでいただきたいと思っています。

メーカー希望小売価格 : 115,000円(税抜)
・16マルチトラックレコーダー(MTR)搭載。 SDカード(Class 10以上)に最大48kHz/24bit、16マルチトラック同時レコーディングが可能
・最大8トラックのパンチイン・パンチアウトが可能
・16入力/14出力USBオーディオインターフェース機能でDAWとのオーディオデータの入出力が可能
・14ch ミキサー入力(10 モノラルXLR/TRS-バランス、2TRS-バランス ステレオペア)
・10ch マイクプリアンプ、CH1~CH8にはクリアな音色のTASCAM Ultra-HDDAマイクプリアンプを装備
・オーバーロード(OL)付シグナルLED搭載ゲイン調整ノブ(CH1~CH12)を装備
・各チャンネルの入力ソース切り替えに(LIVE/PC/MTR)モードスイッチを装備
・便利な1ノブコンプレッサーをモノ入力チャンネル(CH1~CH8)に装備
・入力には3バンドEQ装備 、CH1~CH8にはミッドパラメトリックEQ(中域周波数可変型)装備
・100Hz ローカットフィルター (CH1~CH12)
・全てのXLRマイク入力には+48Vファントムパワー対応
・19インチ ラックマウント対応(ラックマウントキットは別売オプション)
関連する記事
2019/04/24
2018/11/12
2018/07/03
2018/03/22
2017/10/06
2017/06/20
2017/06/20
ニュース
2023/12/25
2023/12/20
2023/12/18
インタビュー
2023/03/23
2022/09/15
2022/05/26
2022/01/26
特集/レビュー
2023/04/03
レクチャー
2022/11/15
2022/11/01